世界屈指の美食の街サンセバスチャン 🇪🇸。世界一周の旅の中でも、”この街は外せない”とずっと楽しみにしていた場所です!
バルの聖地と呼ばれるほど、旧市街を中心にたくさんのバルが並び、世界中の食通たちがピンチョス(小皿で提供されるおつまみ♡)目当てに訪れます♪
バスク地方の街で、日本でも大人気のあのスイーツ「バスクチーズケーキ」発祥のお店がある場所なんですよ♡
”人々が集まる場所には文化が生まれる” ここサンセバスチャンでは、食こそがその中心にあると強く感じました。TXIKITEO(チキテオ)というはしご酒の文化もその一つと言えるでしょう。
そんな美食の街で、バル巡りはもちろんのこと、シードル体験、料理教室でのスペイン料理づくりを体験してきました。
今回の記事では、料理教室で学んだことを中心にサンセバスチャンで生まれたバル文化、人々の繋がりについてスペイン食文化の真髄を紐解いていきます!
本サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
スペインの食文化、内と外の2つの「空間」
家庭のキッチンは、女性の権威の象徴

サンセバスチャンの家庭では… 食事の支度は”女の仕事”
キッチンは女性の聖域的場所で、男性はキッチンに入ることが一切出来なかったのだそう。
食に対する強いこだわりがあるこの地では、家庭で料理をすること=家の主導権を持つこと。女性たちは、「家の味」を守るという責任とともに、家庭の支配権も握ってきたのです。
 まほ
まほキッチンを制する女性は、家の大黒柱的な存在だったみたい!!
男がそこに踏み込むことは、ある意味“礼儀知らず”でもあるとされてきたのです。



小腹が空いたな…ってなって自分で冷蔵庫を覗くのさえもNGだったなんて!泣
\データ無制限でお得なeSIM/
5%OFFで購入できます!
男性が”料理をするため”に作った場所


”料理をしたくても家庭ではできない”なら…
そんな男性たちが “居場所を求め”、外に自分たちの手で料理する場所をつくったのです。
そうして誕生したのが「バル」という空間!!


家庭での不自由さが生んだ、新しいキッチンの形が今日のバル文化へと繋がっていったのです。



自由に料理をしたいという想いが文化にまで発展するとは…!✨
食文化を支える生産者の存在
料理教室では食材調達のため、市場にも訪れました!
受け継がれる生産者との繋がりが食卓をつくる
市場を歩いていると、気になることが。


それは、八百屋さんなら同じ野菜や果物が並んでいて、精肉屋さんなら同じ部位のお肉が並んでいるなど、ほとんどのお店で食材が被っていたこと。
販売している食材が同じように見えるけど、お店の商売は成り立つのだろうか?
地元のレストランオーナーによると、“生産者との深い信頼関係の上に成り立っている” からこそ可能な仕組みだと言います。
サンセバスチャンの地では、「誰から買うか」が重要なのです。


野菜を買うのも、肉も魚も、誰から買うのか決まっていたのです。
料理教室に参加した際にもに、他のメンバーがシェフに「いい野菜の見分け方」を聞いたところ、 ”そこで買うものは全て信頼している、だから全ていい食材”と全信頼を生産者の方においていました。
もちろん見極め方も教えてもらったのですが、確かにそこにある食材は全てシェフがおっしゃる通りのものでした。
“頼んで仕入れる”信頼のシステム


もし、そのお店に欲しい食材が置いてなかったとしても、他のお店では購入しない。
生産者との深い信頼関係があるサンセバスチャンでは、いつものお店に行って必要なものがなかったとしても、それを生産者に伝えて用意してもらうのです。



これこそ、まさに信頼関係あってのものだよね!
「生産者を信頼する」そして、生産者の方もそれに応える。



すごくいい循環を生んでいるなと強く思いました。
女性が食文化の根幹を担っている


サンセバスチャンといえば、美食の街!100軒以上構えるバルで食べ歩きをするために訪れる人も多いほど。
テレビでも芸能人がハシゴ酒を楽しむ様子が度々取り上げられているので、年々訪れる日本人も増えています。
そんなサンセバスチャンのバルでは、料理人の多くが男性です。



行ったほとんどのお店では、そうでした!
まさに、サンセバスチャンの食文化の変遷そのもの。とても興味深いですね!
反対に、市場で見かけた生産者の多くは、女性だったのですが、それはきっと食事の支度をするという女性の役割が変化していった結果なのでは。
サンセバスチャンでは、シェフよりも誰よりも生産者が一番偉い立場にあるとシェフが仰っていました。
”金曜日の市場”が語る週末の家族物語
私たちが市場を訪れたのは金曜日、そこにはお年を召した方が多かった印象です。
賑わう金曜日の市場


スペインの家庭では、週末になると家族が揃って食事をする習慣があるのだそう。
週末は家族が集まる特別な時間だからこそ、腕によりをふるってワイワイみんなで食事を楽しむ家庭が多いのです。


サンセバスチャンを離れて働く子どもたちも、比較的近くの街で暮らしていて、家族との距離はそう遠くないと言います。毎週でなくとも定期的に週末に集う習慣があるというのはステキですね♡
子どもたちや孫たちが好きな料理を準備するために、金曜日になるとおじいちゃんおばあちゃんが市場に向かうのです。



エコバッグいっぱいに食材を買うのが家族のためってイイね!
“世代”と“時間”をつなぐ食事


週末の食卓は、レシピが受け継がれる場でもあります。
単に食事をするだけでなく、伝統料理を楽しむこともスペインで大切にされていることの一つ。地元の食材を使った地元ならではのグルメは家族の、そして自分たちの街の財産として守られてきました。
こうして家庭の味が子の世代、孫の世代へと引き継がれていく。スペイン料理の真髄はここにあるのかもしれません。
サンセバスチャンは ”シードル”も一流!


バルだけじゃない。忘れてはならないのが、この地方の名物「シードル」。
その歴史は中世にまで遡ると言います。安全な水さえ確保が難しい当時は、りんごを破砕して発酵させるだけの発泡酒・シードルがごく一般的に親しまれていたのだとか。
また、貯蔵もきくアルコール飲料だったことから、スペイン北部・フランス南部の地域においては、ビタミン豊富なシードルは長い船旅の際の栄養補給として貢献していました。
シードルは、りんご由来の柔らかな甘みと酸味があって飲みやすく、料理との相性も抜群!
恥ずかしながらシードルが有名なことを訪れる直前まで知らなかったのですが、知人に教えてもらい、サンセバスチャンのシードル酒場へ。
ここでの体験が、冒頭でも述べた ”人々が集まる場所には文化が生まれる” そんなサンセバスチャンの文化の発展に大きな結びつきがあると感じました。
それは、サンセバスチャンでは食が中心である、と感じた真骨頂でもあります。
\データ無制限でお得なeSIM/
5%OFFで購入できます!
“Txotx!”の掛け声で始まるシードル体験


サンセバスチャンの街からは、車で数十分離れた場所にあるAstigarraga(アスティガラガ)と言うエリア。ここには多くのシードレリア(シードルバル)が集まっています。
今回教えてもらったのは「Alorrenea Sagardotegia」というお店。
着いたときに感じた外からのお店の雰囲気はとても静かでしたが、大きな扉を開けて一歩足を踏み入れるとびっくり!ほとんどの席が埋まるほどの賑わいでした!
とりあえずは、シードルを注文することにしたのですが、なんとそれが”8€”で飲み放題!閉店まで好きなだけ飲んでいいとのこと。



1〜2杯楽しめたらいいなと思っていたので、テンションMAXに!
そして、面白いのがその飲み方!
グラスを片手に大きな樽の前に集まって、樽から直接グラスに注いで飲むスタイルなのです。
①店員さんが蛇口の鍵を開けて、捻るとシードルが飛び出してくる。
②それを上手くグラスでキャッチする。
③前の人が注ぎ終わりそうになったら、次の人がそのままグラスでキャッチ!
勢いよく注がれたシードルは、爽やかな香りを放ち、幸せな気持ちに。
まずは、その場で1杯飲み干すのが現地流。


TXOTX(チョーチ)!
この掛け声が、お酒を飲みたい時の合図です。
誰かが掛け声を発すると、飲みたい人が続々と樽の前に集まっていきました。
自分のペースで大丈夫。掛け声を知らずに樽の前にひとりでふらりと行ったら、続くように後ろから人がゾロゾロと集まってきました。笑
誰かが樽の前に立てば、自然と人が集まってくる。そして、シードルの入ったグラスを片手に、自然と会話も弾みます♪
実際に、シードル酒場ではたくさんの方が声をかけてくれました。これ美味しかったよ!私はこのお店が一番だと思うんだよね、そう思わない?など一緒に楽しもうという温かい気持ちが伝わってきます♡
私たちがバックパックを持ってお店に入ったのもあり、いろんな人から「君たち次の目的地どこ?送るよ」と声をかけてくれたり、仲良くなったおじちゃんはシードル酒場定番の胡桃をたくさんくれたり、次のおかわりに行こ!と誘ってくれたり。



みんなフレンドリーで優しかったなぁ💭
必食!熟成赤肉ステーキがジューシーすぎる


シードル酒場で、欠かせないのが熟成の赤肉ステーキ。
石窯で何時間もかけてじっくり焼き上げられたお肉は、とにかく柔らかくてジューシー…!
焼き加減はもちろん、とにかく塩加減も抜群で、今まで食べた骨付きステーキの中でダントツで(忖度なしに)超絶美味しかったです。
そして、これがまたシードルに合うんです!!!



美味しすぎて、もう食べ飲みする手が止まりません✨
骨付き肉 Txuleta の他にもシードレリアといえばの定番があるようで、ほとんどのお店で味わえますよ♪
▼ほぼみんなが頼む
・パン Ogia(バケット)
・タラとピーマンのフライ Bacalao Pimenetos
▼これは通常のバルでも頼めるけどシードレリアでも人気
・トルティージャ Tortiila(スペイン風オムレツ)
・チョリソー Chorizo
▼デザートはこれ♡
・殻付き胡桃
・チーズとメンブリーヨ(チーズ&ジャム)
スペインの”食”が生み出す文化のカタチ


家庭とバル、これら2つの空間が生み出したサンセバスチャンの食文化。
”男は外で料理をし、女は家庭で味を守る”空間は違えど、世代を超えて受け継がれる”食”の時間はとてもユニークだと思いませんか?✨
”食”を中心に広がる人との繋がり。
日本とはまた違う”人と食との物語”がありました。
ぜひ、サンセバスチャンという”美食の街”で存分に”食文化”を満喫してみてはいかがでしょうか♪
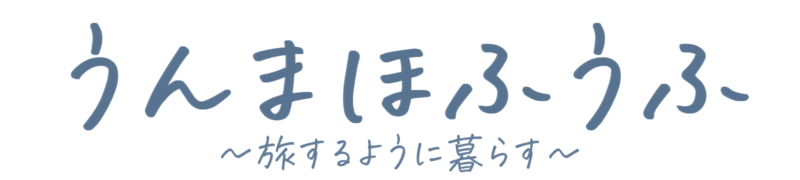

コメント